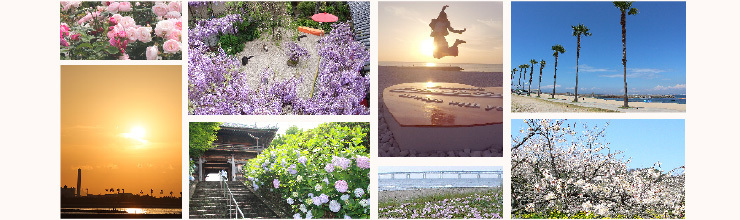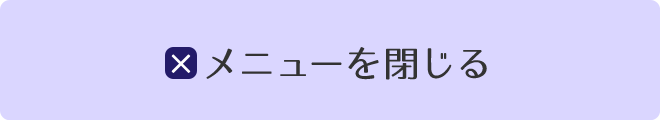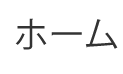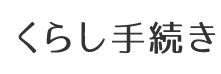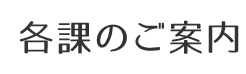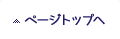定額減税を補足する調整給付金(不足額給付)について(申請受付終了しました)
10月31日で申請受付終了しました。
「不足額給付」とは、令和6年度に実施した、定額減税しきれない方と見込まれる方への給付(当初調整給付)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
令和6年度に、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を調整給付金(当初調整給付)として支給しています。
不足額給付(1)について
令和6年度に実施した「調整給付」(注1)の支給については、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待った場合、速やかな支援が行えないことから、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しています。
このため、「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。
(注1)令和6年度に実施した「調整給付」については、定額減税の対象者で、定額減税額が
「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る
(控除しきれない)と見込まれる方への給付金。
・給付金算出方法
所得税分定額減税可能額 -令和6年分推計所得税額 = 1.
個人住民税所得割分減税可能額 -令和6年度分個人住民税所得割額 = 2.
1. + 2.(合計を1万円単位に切り上げ)= 支給額
(所得税は令和5年分所得税額を用いて令和6年分を推計)
なお、「本来給付すべき額」が「実際に給付した額(調整給付)」を下回った場合には、余剰金の返還は求めない。
<対象となりうる例>
1.令和5年と令和6年で所得が大きく変動した場合
(a)令和5年所得よりも、令和6年所得が減少した場合(事業不振、退職等)
(b)令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合(学生の就職等)
(c)税の更正(修正申告)により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した場合
2. 令和6年中に扶養親族が増えた場合
(d)子どもが生まれたことで扶養親族が増えた場合
(a)令和5年所得よりも、令和6年所得が減少した場合(事業不振、退職等)
|
|
令和5年所得 |
令和6年所得 |
|
推計所得税 |
50,000円 |
35,000円 |
|
定額減税可能額 (所得税分のみ) |
90,000円 |
90,000円 |
|
調整給付 |
40,000円 |
55,000円 |
定額減税可能額=(本人+同一生計配偶者+扶養親族)×3万円
55,000円-40,000円=15,000円 ⇒ 20,000円
【解説】令和5年所得に基づく推計所得税額が5万円、所得税額分のみの定額減税可能額が9万円、調整給付は4万円であったが、令和6年所得が確定し、所得税額(実績)が3万5千円、所得税額分のみの定額減税可能額が9万円となり、調整給付(実績)は5万5千円となった場合、調整給付の4万円と調整給付(実績)5万5千円の差額である1万5千円が不足額給付として給付されるが、端数は1万円単位で切上げされるため、2万円が不足額給付として給付されます。
(b)令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合(学生の就職等)
|
|
令和5年学生 |
令和6年社会人 |
|
所得税額 |
推計所得税額 0円 |
所得税額(実績) 50,000円 |
|
定額減税可能額 |
定額減税対象外 0円 |
所得税分 30,000円 住民税分 10,000円 |
|
調整給付 |
0円 |
10,000円 |
定額減税可能額(所得税分)=(本人+同一生計配偶者+扶養親族)×3万円
定額減税可能額(住民税分)=(本人+同一生計配偶者+扶養親族)×1万円
10,000円-0円=10,000円
【解説】令和5年中は所得がなかったため、本人として推計所得税、調整給付ともに0円だった者が、就職等により、令和6年所得税額が5万円となった。この場合、定額減税可能額(所得税分)の3万円分が減税され、所得税額は2万円となる。
一方で定額減税可能額(住民税分)については、令和6年度分住民税が発生していないことで、減税することができないため、住民税分の1万円が不足額給付として給付されます。
(c)税の更正(修正申告)により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した場合
・令和6年度個人住民税の修正申告等により、個人住民税(所得割)が減少した
|
|
令和6年度住民税 調整給付時 |
令和6年度住民税 不足額給付時 |
|
個人住民税(所得割) |
40,000円 |
30,000円 |
|
定額減税可能額 (住民税分のみ) |
40,000円 |
40,000円 |
|
給付金 |
0円 |
10,000円 |
定額減税可能額=(本人+同一生計配偶者+扶養親族)×1万円
10,000円-0円=10,000円
【解説】令和6年度住民税の当初決定時には個人住民税所得割額が4万円、個人住民税分のみの定額減税可能額が4万円のため、調整給付は0円であったが、当初決定後に税の修正申告を行ったことで、個人住民税所得割が3万円に減少した場合。
本事例では、減少後の個人住民税所得割で不足額給付の算定を行うため、個人住民税所得割が3万円、個人住民税分の定額減税可能額が4万円、不足額給付時の調整給付額は1万円となり調整給付0円と不足額給付時調整給付額1万円の差額の1万円が不足額給付として給付されます。
(d)令和6年中に扶養親族が増えた場合
|
|
調整給付金算定時 |
不足額給付金算定時 |
|
所得税額 |
推計所得税額 70,000円 |
所得税額(実績) 70,000円 |
|
定額減税可能額 (所得税分のみ) |
90,000円 |
120,000円 |
|
調整給付 |
20,000円 |
調整給付(実績) 50,000円 |
定額減税可能額=(本人+同一生計配偶者+扶養親族)×3万円
50,000円-20,000円=30,000円
【解説】令和5年の扶養状況は2人(妻、子1人)だったため、所得税分のみの定額減税額は9万円((本人+同一生計配偶者1人+扶養親族1人)×3万円)となるが、その後、令和6年中に子どもが生まれ、扶養人数が1人増えたため、所得税分のみの定額減税額が12万円((本人+同一生計配偶者1人+扶養親族2人)×3万円)となった場合。
本事例では、令和5年所得に基づく推計所得税額が7万円、定額減税額が9万円で調整給付は2万円に対して、令和6年の所得税額(実績)が7万円、定額減税可能額が12万円となったことで、調整給付(実績)は5万円となる。これより、調整給付2万円と調整給付(実績)5万円の差額の3万円が不足額給付として給付されます。
(注)個人住民税の定額減税額は令和5年12月31日現在の状況で判定するため、令和6年中に扶養親族数に変更があった場合でも、その額は変動しません。
不足額給付(2)について
すべての要件を満たす方に、原則4万円を給付します。ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円となります。
・所得税、個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)
→本人として定額減税対象外である方
・「扶養親族」の対象外(税制度上)
→青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方
・低所得世帯向け給付(注2)の対象になっていない方
(注2)低所得世帯向け給付金とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)になります。
<対象となりうる例>
(e)課税世帯に属している「事業専従者(青色・白色)」
(f)課税世帯に属している「合計所得金額48万円超」の方のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の方(定額減税適用前、税額控除後)
(e)課税世帯に属している「事業専従者(青色・白色)」
〔個人事業主〕
・個人事業主(配偶者を専従者として雇用)
・個人住民税(所得割)課税者
⇒定額減税の対象
定額減税可能額
所得税分(1人)×3万円=3万円
住民税分(1人)×1万円=1万円
計4万円
★税法上、専従者は扶養できない
〔個人事業主の配偶者〕
・事業専従者 : 控除対象配偶者や扶養親族等に含まれない
・年間給与 : 概ね100万円以下の場合
所得税、個人住民税ともに非課税
⇒定額減税の対象外
★個人住民税(所得割)課税者が世帯にいるため、低所得世帯向け給付の対象外
・個人事業主の配偶者は不足額給付(2)の対象となる
【解説】納税者である個人事業主の事業専従者(個人事業主の配偶者)であって、自身の給与収入がおおむね100万円に満たない者(所得税、住民税が非課税)が、世帯内に納税者(個人事業主)がいることで、低所得世帯向け給付金の対象ともならなかった場合、不足額給付の対象となります。
(f)課税世帯に属している「合計所得金額48万円超」の方のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の方(定額減税適用前、税額控除後)
・世帯主・配偶者の2人世帯に世帯主の父が同居の場合
〔子〕
・個人住民税(所得割)課税者
⇒定額減税の対象
定額減税可能額
所得税分(2人)×3万円=6万円
住民税分(2人)×1万円=2万円
計8万円
〔子の配偶者〕
・収入なし、非課税の場合
・子は扶養できる
・所得税、住民税ともに課されない
⇒定額減税の対象外
・定額減税対象者の配偶者
⇒減税対象人数に含まれる
〔子の父〕
・年金収入158万円から概ね170万円以下、所得税・住民税(所得割)非課税の場合
・子は扶養できない(所得超過のため)
・年金収入により合計所得48万円超
⇒子の定額減税における扶養親族等の対象外
・所得税、住民税(所得割)ともに課されない
⇒定額減税の対象外
★個人住民税(所得割)課税者が世帯にいるため、低所得世帯向け給付の対象外
・子の父は不足額給付(2)の対象となる
【解説】子の父の合計所得金額は48万円を超えるが、所得控除や、子の父の状況により所得税・住民税(所得割)ともに非課税で、子の父本人及び子の扶養親族としても定額減税の対象でないものが、納税者(子)等と同居しているため、低所得世帯向け給付金の対象にもならなかった場合、本人(父)は不足額給付の対象となります。
手続き等
【支給のお知らせが届いた方】
手続不要
口座変更等がある場合のみ、返信用封筒にて返信してください。
【確認書が届いた方】
手続必要
確認書の内容を確認し、必要事項を記入して返信用封筒にて返信してください。
【申請書が届いた方】
手続必要
支給要件に当てはまる方は、申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、返信用封筒にて返信してください。
【何も届かない方】
手続必要
不足額が発生すると見込まれるにもかかわらず、お知らせ等が届かない場合があります。不足額給付(2)に該当する方については、申請が必要です。市から書類は届きません。給付金担当に連絡下さい。
給付予定
【支給のお知らせが届いた方】
令和7年8月14日に入金予定です。
【確認書・申請書が届いた方】
書類内容の確認後、概ね3週間程度でご指定の金融機関口座に振り込みます。
令和7年10月31日までの提出をお願いいたします。
申請期間
令和7年10月31日まで【必着】
お問い合わせ
本市の連絡先
泉南市福祉保険部生活福祉課給付金担当
場所:泉南市役所1階
電話番号:072-447-8131
時間:午前9時から午後5時半まで(土、日、祝を除きます。)
振り込め詐欺にご注意ください!
申請内容に不明な点があった場合、臨時特別給付金担当から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話やメール、郵便が届いたら、迷わず泉南市役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉総務係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-3474
ファックス番号:072-483-7667
e-mail:seikatsu-f@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから