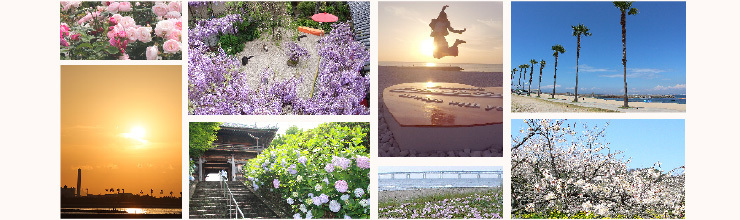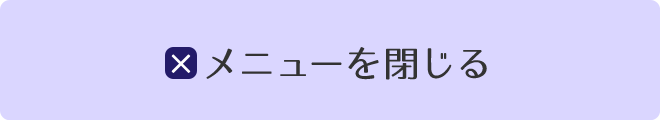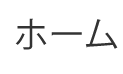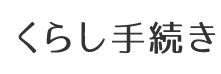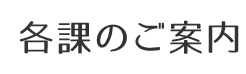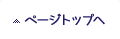幼児教育・保育の無償化について
国の制度改正により、令和元年10月1日から幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳児~5歳児と住民税非課税世帯に属する0 歳児~ 2 歳児の利用料が無償化の対象となっておりますので、国が定める方針についてお知らせします。

1.幼稚園(新制度移行園)、認定こども園(教育認定)等
【対象者】
3歳児から5歳児の子ども(満3歳に到達した日から無償化の対象となります。)
【無償化対象外の経費】
通園送迎費、行事費、食材料費等です。
【食材料費の免除】
年収360万円未満相当の世帯や、年収360万円相当以上の世帯で3歳から小学校3年生までの子どものみを数えて第3子以降の子どもについては、食材料費(おかず・おやつ代に限る)が免除されます。
【手続き】
既に幼稚園等を利用されている方は、新たな手続きは不要です。
2.幼稚園(新制度未移行園)
【対象者】
3歳児から5歳児の子ども(満3歳に到達した日から無償化の対象となります。)
【無償化される利用料】
保育料・入園料に対し、月額上限25,700円を市から施設へ支払います。
幼稚園から請求される保育料が25,700円を超える場合、超えた分(差額)は幼稚園に支払っていただく必要があります。
- 入園料は入園初年度に限り、月額に換算して無償化の対象となります。
【無償化対象外の経費】
通園送迎費、行事費、食材料費等です。
【食材料費の免除】
年収360万円未満相当の世帯や、年収360万円相当以上の世帯で3歳から小学校3年生までの子どものみを数えて第3子以降の子どもについては、食材料費(おかず・おやつ代に限る)が免除されます。
免除額は食材料費(おかず・おやつ代=月額上限4,500円)となります。なお、食材料費は、施設により異なる場合がございますので、施設にお問い合わせください。
【手続き】
無償化の対象となるには、事前に申請が必要です。「【新制度未移行園等】子育てのための施設等利用給付認定申請書兼副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書」に必要事項を記入の上、 施設の利用開始日が属する月の前月の15日まで に施設へご提出ください。
- 【新制度未移行園等】子育てのための施設等利用給付認定申請書兼副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書
【令和7年度用】
【新制度未移行園等】子育てのための施設等利用給付認定申請書兼副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書 (PDFファイル: 236.2KB)
3.幼稚園、認定こども園(教育認定)の預かり保育
【対象者】
保育の必要性が認定され、かつ、次のいずれかに該当する子ども
- 3歳児から5歳児の子ども
- 住民税非課税世帯に属する、満3歳の子ども(満3歳に到達した次の3月31日まで)
【対象となる施設・サービス】
在園する幼稚園等が実施する預かり保育(幼稚園等を利用している方で、在園する幼稚園等が預かり保育を実施していない等の場合は、預かり保育の利用料のほか、認可外保育施設等の利用料も無償化の対象となる場合があります)
≪確認事項≫
預かり保育を平日教育時間とあわせて1日8時間以上かつ年間200日以上提供している幼稚園・認定こども園を利用している場合、認可外保育施設等の利用料は無償化の対象外となります。
【無償化される利用料】
実際の利用料と「日額単価450円乗じる利用日数」を比較して、低い方の金額が月額11,300円(満3歳に到達した次の3月31日までは月額16,300円)まで無償化されます。
注意:通園送迎費、行事費、食材料費等は対象外となります。

【支給方法】
公立幼稚園・公立認定こども園を利用する方
実際の利用料が無償化上限(450円乗じる利用日数)より低い場合は、負担額は0円になります。実際の利用料が無償化上限を超えた場合は、超えた分を在籍園にお支払いいただきます。(他市の公立施設に関しては、別途お問い合わせください。)
民間幼稚園・民間認定こども園を利用する方
預かり保育の利用料は一旦保護者様自身で施設にてご負担いただき、保護者様からのご請求に基づき、無償化分を市から返金するという償還払いとなります。
注意事項
- 認定がされた場合でも、在園する幼稚園等において預かり保育を実施するために必要な保育士や施設の広さに限りがあるため、希望通り預かり保育を利用できるとは限りません。 そのため、施設により就労状況等預かり保育の優先度の高い方から利用できる方を決めるなど、各施設の選定方法により利用できる方を制限することがありますのでご理解下さい。
- 幼稚園等をご利用の方で、在園する幼稚園等が預かり保育を実施していない等の場合は、預かり保育の利用料のほか、認可外保育施設等の利用料も無償化の対象となる場合があります。
【手続き】
預かり保育の無償化の対象となるには、事前に申請が必要です。
【新制度移行園・認定こども園・認可外保育施設等】及び【新制度未移行園等】の「子育てのための施設等利用給付認定申請書」に必要事項を記入の上、 利用開始日が属する月の前月の15日まで に保育子ども課へご提出ください。
- 【新制度移行園・認定こども園・認可外保育施設等】子育てのための施設等利用給付認定申請書
- 【新制度未移行園等】子育てのための施設等利用給付認定申請書兼副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書
- 保育の必要性の認定に関する必要書類(申請書の裏面にてご確認ください。)
【令和7年度用】
【新制度移行園・認定こども園・認可外保育施設等】子育てのための施設等利用給付認定申請書 (PDFファイル: 233.0KB)
※各種必要書類につきましてはページ最下部でダウンロードが可能となっております。
4.認可保育所、認定こども園(保育認定)等
【対象者】
- 3 歳児~ 5 歳児の子ども(満3 歳に到達した次の4 月1 日から無償化の対象となります)
- 住民税非課税世帯に属する0 歳児~ 2 歳児の子ども
【無償化対象外の経費】
通園送迎費、行事費、食材料費等です。
【食材料費】
保育所や認定こども園(保育所部分)等を利用する3歳児から5歳児についての食材料費は、利用料の一部としてお支払いいただいていましたが、無償化後は食材料費(おかず・おやつ代に限る)を施設へお支払いいただくことになります(0歳児~2歳児については、これまでと同様、利用料に含まれます)。

【食材料費の免除】
年収360万円未満相当の世帯や、年収360万円相当以上の世帯で小学校就学前の子どものみを数えて第3子以降の子どもについては、食材料費(おかず・おやつ代に限る)が免除されます。
【手続き】
既に幼稚園等を利用されている方は、新たな手続きは不要です。
5.認可外保育施設等
【対象者】
認可保育所、認定こども園、企業主導型保育、預かり保育を実施している幼稚園等を利用できておらず、保育の必要性が認定され、かつ、次のいずれかに該当する子ども
- 3歳児から5歳児の子ども(満3歳に到達した次の4月1日から無償化の対象となります。)
- 住民税非課税世帯に属する、0歳児から2歳児の子ども
【対象となる施設・事業】
- 都道府県等に届出をした認可外保育施設(ベビーシッター、認可外の事業所内保育等)
- 一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(利用内容により一部無償化の対象外)
複数サービスの併用も上限額の範囲で無償化の対象となります 。
【無償化される利用料】
3歳児から5歳児は月額37,000円、0歳児から2歳児は月額42,000円を上限に利用料が無償化されます。

【無償化対象外の経費】
通園送迎費、行事費、食材料費等です。
【支給方法】
認可外保育施設等の利用料は、一旦保護者様自身で施設にてご負担いただき、保護者様からのご請求に基づき、無償化分を市から返金するという償還払いとなります。
【手続き】
無償化の対象となるには、事前に申請が必要です。
「【新制度移行園・認定こども園・認可外保育施設等】子育てのための施設等利用給付認定申請書」に必要事項を記入の上、 利用開始日が属する月の前月の15日まで に保育子ども課へご提出ください。
- 【新制度移行園・認定こども園・認可外保育施設等】子育てのための施設等利用給付認定申請書
- 保育の必要性の認定に関する必要書類(申請書の裏面にてご確認ください。)
- 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書
- 0歳児から2歳児の子どもで、当該年の1月1日に泉南市以外の市区町村に住民票があった場合⇒1月1日時点に住民票がある市区町村の非課税証明書…父母1部ずつ
【令和7年度用】
【新制度移行園・認定こども園・認可外保育施設等】子育てのための施設等利用給付認定申請書 (PDFファイル: 233.0KB)
保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書 (PDFファイル: 82.2KB)
※各種必要書類につきましてはページ最下部でダウンロードが可能となっております。
6.障害児通所支援施設
【対象者】
3 歳児~ 5 歳児の子ども(満3 歳に到達した次の4 月1 日から無償化の対象となります)
- 0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもの利用については、すでに無償化済です。
【対象となる施設・サービス】
児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援事業、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設の利用料
- 障害児通所支援施設に係る無償化と幼児教育・保育等の無償化は、それぞれ独立したものですので、それぞれが無償化の対象となります。
【手続き】
既に障害児通所等のサービス等を利用されている方は、新たな手続きは不要です。
各種必要書類
【注意】保育を必要とする事由が就労の方は提出が必要です。
【注意】保育を必要とする事由が就労(内職)の方で、就労証明書の提出が困難な方は提出が必要です。
【注意】就労(自営)、配偶者や祖父母が経営する会社に勤務している方(専従者等)、就労(内職)、農業専従者の方は提出が必要です。
【注意】保育を必要とする事由が同居親族等の介護・看護の方は提出が必要です。
【注意】保育を必要とする事由が求職活動の方は提出が必要です。
その他の必要書類
【注意】提出書類に不備がある等の特筆すべきことがある方は提出が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
保育子ども課
保育子ども係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-3471
ファックス番号:072-447-8117
e-mail:jidou-f@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから