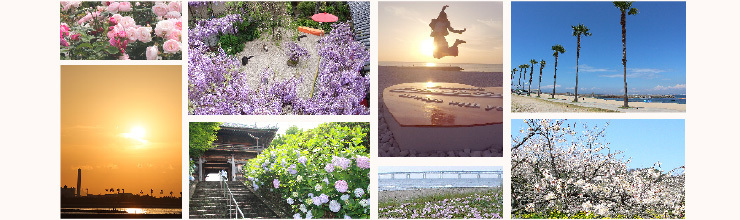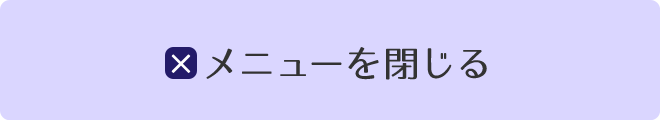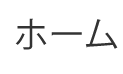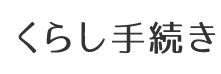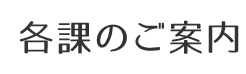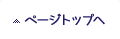地域での助け合い
地域住民による防災
阪神・淡路大震災では、生き埋めになって自力での脱出が困難になった人のうち、消防や警察、自衛隊など防災関係者によって救助されたのは約20%であり、80%近くの人は近隣の住民によって救出されています。
消防や警察など公的機関による救出・救護がすぐに行われないときにいちばん頼りになるのが、地域住民による助け合いなのです。
日頃からの地域交流が大切です

突然起きる災害に対して、いきなり迅速・適切な対応をとるのは難しいことです。日常の交流を通して地域の連帯感を培っておくことが最大の災害対策です。
また、避難行動要支援者の方に気を配るとともに、避難経路に障害物がないか、など避難行動要支援者の視線でいっしょに考えるようにしましょう。
特に防災訓練には積極的に参加するようにしましょう。また、区であらかじめ自主防災組織をつくりましょう。
住民の協力による救出・救護
多くの建物が倒壊したような混乱した状況の中でも、住民一人ひとりが協力して救出・救護活動にあたれば、被害者の救命率を高めることができます。
避難行動要支援者を守りましょう
年齢や障害などによって、災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難で、避難に支援の必要な方を避難行動要支援者といいます。一般に高齢者や障害のある方、乳幼児や妊産婦の方々などが該当します。
地域で協力しあいながら、近所の高齢者、障害のある方などの安否確認、避難所への移動を支援しましょう。また、いざというときに避難行動要支援者をみんなで支えられるよう、日頃からの地域のなかで交流を深めておくことが大切です。
避難行動要支援者の支援について
高齢者

- おぶって安全な場所まで避難する。
- 複数の介助者で対応する。
肢体の不自由な方(車椅子)

- 階段では2人以上が必要。上りは前向き、下りは後ろ向きにして移動する。
- 介助者が1人の場合は、ひもなどを用意し、おぶって避難する。
目の不自由な方

- 声をかけ情報を伝える。
- 誘導する場合は、杖を持った方の手には触れず、ひじのあたりを軽く持って、半歩手前をゆっくり歩く。
耳の不自由な方

- 話すときは口をハッキリと開け、相手にわかりやすいようにする。
- 手話、筆談、身振りなどの方法で正確な情報を伝える。
避難所でのマナー
ゆずりあい

避難所はみんなで使うところです。限られたスペースしかありません。トイレの順番などできるだけゆずりあいましょう。
おもいやり

避難所では大きな声を出したり、走り回ったりするとまわりの人たちの迷惑になります。お互いにおもいやりの気持ちで過ごしましょう。
たすけあい

ケガをしている人や体の不自由な人、また、病気の人なども避難所には集まります。みんなが少しでも快適に過ごせるように助け合いましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
危機管理係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-479-3601
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kikikanri@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから