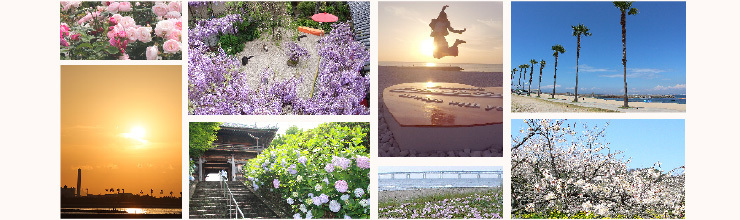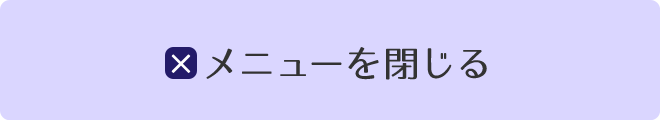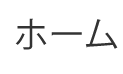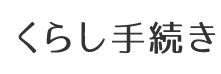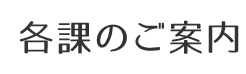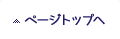市政運営方針
令和7年度市政運営方針
はじめに
令和7年第1回泉南市議会定例会の開会にあたり、私の所信の一端を申し述べるとともに、令和7年度の市政運営方針を申し上げ、議員各位並びに市民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。
私は市長に就任して以来、持続可能なまちづくりを目指して、行政運営の組織体制を再編・強化し、行政経営基盤の強化に重点を置いた取組を進めてまいりました。就任当初に私が掲げたマニュフェスト60項目については、現時点で約9割が進捗しているところであり、一定の成果を得ることができたものと考えております。これも市民の皆様をはじめ、市議会議員の皆様のご支援、ご協力によるものと、心より感謝申し上げます。
任期の終盤となる令和7年度の市政運営については、これまでの取組を継続するとともに、まだある本市の行政課題に真摯に取り組み、一歩一歩確実に、市民の皆様に泉南市に住んでよかったと言っていただけるまちを目指していきます。
また、今年は4月に大阪・関西万博が開幕となり、あわせて本市は7月に市制55周年を迎えます。関西国際空港を利用する旅客はさらなる増加が見込まれ、大阪に関心が集まる年となります。この機会を逃すことなく、積極的に本市の魅力を発信し、本市の地域資源を活用した賑わいの創出に取り組み、また、ふるさと納税の伸長や企業投資を呼び込むなど、本市の発展の可能性をさらに広げてまいります。
また、未来への投資として、教育の質の向上や子どもたちの学びのための環境整備、大阪・関西万博を契機とした子どもたちへのグローバル教育の実施、子育て支援の充実など、子どもたちが持つ可能性を存分に発揮できるまちを目指すとともに、子どもの権利救済委員会を設置するなど、子どもにやさしいまちづくりに向け、各種施策を推進してまいります。
また、南海トラフ沿いの大規模地震は今後30年以内に発生する確率が80%程度と切迫性が高まっていることから、安全・安心に暮らせるまちづくりは本市が抱える重要な課題となっています。そのため、市民の皆様へ重要な防災情報を迅速かつ的確に提供するため、防災アプリの普及に力を入れるとともに、防災無線を更新し、発災後の市民の皆様の避難生活に備えた取組も進めてまいります。
一方、財政状況につきましては、経常的経費の増加が見込まれ、物価高騰や国際情勢等の影響を受けている中で、新たな財源を確保することが難しいため、今後ますます厳しくなることが予測されます。そのため、道路などのインフラを含めた公共施設の整備や更新に関しましては、民間活力導入をはじめとする様々な手法を検討するとともに、限られた財源の中で、効果的で効率的な運営を行うため、広域連携による取組の推進など、さらに視野を広げ、知恵を絞る必要があります。本市を取り巻く人口減少や少子高齢化といった社会情勢を見据えながら、市民の皆様の声に耳を傾け、ニーズを踏まえた政策目標を設定し、サービスの受け手となる市民の皆様が納得される取組を進めてまいります。
それでは、これまでにお示しした私の重点とする取組や行政課題に絡めながら、総合計画の体系に沿って主要な施策をご説明いたします。
分野別政策1 『ひと』を育てる・輝かせる
分野別政策1『ひと』を育てる・輝かせるための施策・事業として次のとおり進めてまいります。
<人権尊重の推進について>
令和4年度に実施した市民人権意識調査の結果において明らかとなった部落差別については、現在策定を進めています泉南市部落差別解消推進基本方針・プランに基づき、差別や偏見のないまちづくりを推進します。
インターネット上での誹謗中傷に関する人権侵害についても、国の法令の整備状況等も踏まえ、今後どのような政策が効果的に人権推進施策を進めることができるか検討を進めていきます。
今年は戦後80年という節目の年でもあります。非核平和都市宣言を行っている本市におきましても、戦争を知らない世代が増える中、市民の皆様に戦争の悲惨さ、平和の尊さについてあらためて考えていただける機会をつくっていきます。
また、令和5年6月に策定した泉南市人権保育・教育基本方針及び同推進プランに沿った人権保育・教育を推進するために、学校園で様々な人権課題についての系統的な取組を進めます。
<男女平等参画社会実現に向けた環境づくりについて>
DV相談をはじめ、女性からの相談は本市のみならず全国的に年々増加している状況です。令和6年4月に施行された、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に基づき、困難な問題を抱える女性について、その発見に務め、その立場に立って相談に応じる女性相談支援相談員の設置に努めます。
<国際交流について>
国際交流につきましては、大阪・関西万博を通じて、姉妹都市であるフィリピン共和国ダバオ市と引き続き教育分野や観光分野においての連携を進めます。また、本市の子どもたちがグローバルな視点をもつことで将来の選択肢を広げることを目的として、海外派遣研修の制度化に向けた検討を進めます。さらに、国際化に向けた方針をとりまとめ、今後の国際化施策の基となる国際化ビジョンの改定を行います。
<子育てしやすい環境の整備について>
母子保健・児童福祉が一体的に子育て家庭に対する相談支援を行う「こども家庭すこやかセンター」において、妊娠期からの切れ目のない支援を実施し、子育てしやすい環境を推進します。
妊娠期から妊産婦等に寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信を行います。また、必要な支援につなぐ伴走型相談支援の推進を図る妊婦等包括相談支援事業とともに妊婦のための支援給付を実施します。
児童福祉につきましては、家庭児童相談室の機能をさらに充実させるとともに、児童虐待の防止に対して、迅速かつ適切な支援を図るため、専門職の研修などによる人材育成に努めます。
さらに、出産時のお祝いとして、生まれた時から長く使っていただける出産記念品をお渡しするとともに、出産後間もない時期の子育て家庭に対する家事・育児などの支援を実施する育児ヘルプ家庭訪問事業を引き続き実施します。また、令和6年4月にオープンした、乳幼児の遊びの広場「SENNAN LITTLE PARK りるぱ」において、親子が楽しく安全に利用できるよう、委託事業者とともによりよい運営を進めます。
また、子育て支援センターにおいては、土曜日・日曜日のひだまりルームを実施し、父親が育児に参加しやすい環境づくりを進めます。
子どもの心身を守り、安全・安心な保育のため、さらなる保育の質の向上と保育環境の充実を図られるよう、障害児加配として保育士を配置する場合の補助金を増額することにより民間保育士の確保に努めます。
保育施設につきましては、国の補助金を活用し民間保育施設の老朽化対策として建物の大規模修繕が行えるよう、支援を行い安全確保に努めます。
子ども総合支援センターにおいては、身体や発達に課題がある子どもの生活や成長における課題について、子どもに関わる関係機関と連携し、専門的な立場から子どもが持つ力を十分に発揮できるように支援します。
<子どもにやさしいまちづくりについて>
子どもにやさしいまちの実現に向けて、子どもが、いじめや虐待、体罰その他の人権侵害を受けたとき、または受けそうな状況に置かれたとき、その子ども自身が必要としている相談と救済を受けることができる、子どもの権利救済委員会を設置します。子どもの権利救済委員会は、子どもの声を直接聴き、子どもと一緒に解決方法を考えることや必要に応じて調査を行い、その結果、必要と認めるときに関係機関等に対して、是正措置の勧告や制度改善の要請などにより、子どもの権利の救済を行っていきます。
また、子どもの声を聴く体制の強化として、家庭・学校・友達にも言えない悩みなどを受け付ける子ども専用のフリーダイヤルを設置するとともに、無料のハガキ封筒付きチラシを小中学校児童生徒へ配布し、公共施設へのチラシ配架も行います。さらに、児童生徒のタブレットにも情報発信し、より一層子ども相談窓口の充実を図ります。
<学校教育について>
学力向上につきましては、令和6年3月に策定しました学力向上プランに沿って、AIドリルを活用した家庭学習を充実させるとともに、市独自の教育検査を実施し、その結果を基にした大学教授や研究機関との授業改善に向けた連携を進め、日々の授業づくりや個別最適な学びに反映させるなど、エビデンスに基づいた教育の充実を図ります。また、令和6年度より始めた「KIRAMEKI☆SUTEKI泉南っ子」事業による自己肯定感の向上や「泉南っ子日本一宣言」の取組推進など、認知・非認知能力の両側面から学力向上施策を進めます。
学習活動のICT化につきましては、国のGIGAスクール構想の実現に向け、大阪府の補助金を活用し、児童生徒のタブレット端末の更新を着実に進めることで、子どもたちの個別最適な学びと協働的な学びの実現を目指します。また、大阪府が実施する共同調達へ参加して導入コストの低減に努め、令和8年4月からの使用開始に向け、取組を進めます。
子どもたちが学校園生活で直面するいじめや暴力行為などの問題行動や不登校に対しては、積極的認知や早期発見に努め、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの専門人材の活用や関係機関と連携した早期対応により解決に努めます。
また、不登校の支援としては、校内教育支援員の配置を充実し、教室以外の居場所づくりのさらなる充実を図ります。
教職員の働き方改革につきましては、スクールサポートスタッフの充実や校務支援システムを導入し効率化を進め、長時間勤務の是正や負担軽減に向けた取組を支援します。さらに、教職員の資質能力の向上のため、学校教育アドバイザーなどを活用した校内研修や個々の教職員のスキルアップに資する研修等、教職員研修のさらなる充実を図ります。
外国語教育につきましては、学校においてJETプログラムの外国語指導助手(ALT)を活用した言語活動の充実に向けた取組を進めるとともに、すべての市立小中学校でフィリピンの学校とのオンラインによる国際交流の機会を作り、外国語でのコミュニケーション能力や意欲の向上を図ります。また、国際交流員(CIR)の派遣を行うことで、市内の様々な団体や学校園における国際交流活動を促進します。そして、外国にルーツのある児童生徒に対しては、安心して学校生活を送り学習することができるように、母語を話せる語学補助員の配置や母語で進学や子育てに関連した情報共有を行う機会をつくり、細やかな支援に努めます。
学校施設につきましては、小中学校屋内運動場の空調設備設置など、良好な教育環境を確保するとともに、施設の保全と修繕に努めます。また、(仮称)西信達義務教育学校等整備事業においては、教職員などの意見を聴取し、施設の設計を進めます。
学校給食につきましては、引き続き、栄養バランスのとれた安全・安心な給食の提供に努めます。また、小学校給食において令和7年9月から民間調理場を活用した食缶によるデリバリー方式での学校給食の提供へ移行します。
<居場所づくりについて>
青少年センターにおいては、子どもの声を形にしていくため、こどもスタッフを組織するとともに、困っている時や悩んでいる時に気軽に相談できる場所として青少年センターあり方基本方針に位置づけ、子ども・青少年の日常的な居場所として確立していきます。また、子どもが安心して遊べるように、埋蔵文化財センター、図書館、人権国際教育課などと連携を図り、各小学校に出向いて行う居場所づくり事業を引き続き展開していきます。
公民館においては、人づくり、地域づくりを発展させます。とりわけ、樽井公民館には常設の自習室を開設し、さらなる自主学習の活動の場を広げます。
図書館においては、地域の情報拠点として、資料及び情報の収集や提供、子どもの読書活動推進に向けた取組を進めます。また、文化ホールにおいては、指定管理者の自主事業の他、市民文化団体とも連携し、様々な文化や芸術に触れる機会を提供します。
<スポーツ振興について>
スポーツ振興につきましては、スポーツ推進委員や体育協会などの関係者と連携して、スポーツ活動の活性化を図るとともに、スポーツによる市民の健康増進へつなげていきます。市民体育館においては、照明器具をLED化し、利用者満足度の向上を図ります。また、泉南スポーツコミッション協会とともに、タルイサザンビーチにおいて泉南オープンウォータースイミング大会を日本水泳連盟公認レースとして開催し、ワールドマスターズゲームズ2027関西に向けての機運醸成と、マリンスポーツの拠点としてタルイサザンビーチの活用による都市魅力の向上に取り組みます。
<青少年の健全育成について>
国際的規模及び全国的規模の競技会、コンクールなどに出場または出展する本市の子どもたちに泉南っ子スポーツ・文化芸術振興奨励金及びオリンピック又はパラリンピック出場奨励金を交付することにより、スポーツ活動の推進、競技力の向上及び文化芸術の振興を図るとともに、全市民が一体となって泉南っ子を応援することで、市全体のスポーツと文化芸術に対する機運を高めます。
令和8年は、コロナ禍により修学旅行など学生生活が制限された世代の子どもたちが二十歳を迎えます。二十歳のつどい式典を盛大に挙行するため、例年よりアトラクションの景品購入費を拡充し、一人でも多くの人の心に残る式典となるよう努めます。
また、留守家庭児童会においては、待機児童解消の観点から、信達第二留守家庭児童会の開設に向け、空き教室の設計を進めます。
分野別政策2 『しごと』を生み出す・にぎわいを創出する
分野別政策2『しごと』を生み出す・にぎわいを創出するための施策・事業として次のとおり進めてまいります。
<農業・漁業の振興について>
農業・漁業の振興につきましては、担い手の確保と生産性向上や付加価値の創造を図るため、地産地消や新たな地域ブランド品の開発を促進するとともに、農業・漁業と観光をつなげた農業漁業体験やマルシェ開催などの交流による活性化など、新たな取組を検討します。特に、地域ブランド品である「泉南あなご」につきましては、株式会社あきんどスシローが大阪・関西万博に出店する「スシロー未来型万博店」への出荷販売が決定しており、また高速道路におけるサービスエリアでの販売やネット販売等を行うことにより、さらなるブランド化を図ります。農業公園につきましては、アンケート結果を参考に活性化について検討を深めます。
<商工業の振興について>
商工業の振興につきましては、商工会と連携し、創業機会の創出に向けた支援を行うとともに、起業創業事業者支援を行います。さらに、商店街の空洞化対策の一環として、空き店舗等活用対策事業を継続し、特に鉄道4駅周辺に特化した支援を行い、商店街の振興と商業の活性化を促進します。また、ふるさと納税型クラウドファンディング制度を利用した支援事業により、意欲のある事業者を積極的に支援して地域産業の振興を図ります。
企業誘致につきましては、令和6年9月に泉南市企業立地促進条例を改正し、りんくうタウン内におけるホテル誘致が実現したことを大きな一歩と捉えています。この成果を基に、さらなる企業進出を促進し、新たな雇用の創出と地域活性化に取り組みます。
<買物困難者対策について>
買物困難者に対する支援として、空き店舗や空き家の活用などにより地域商業の活性化を促進することで、にぎわいの創出を図ります。また、地域公共交通計画の策定に取り組む際、買物困難者の生活利便性の向上が図られるよう、努めます。
<観光の振興について>
観光の振興につきましては、シティプロモーションの一環として、一層の誘客を促進します。本市の有する個性豊かな地域資源の魅力を高め、多方面に発信していくため、市内外との連携を強化し、様々な目線からの磨き上げを行います。
総合交流拠点施設につきましては、周辺のロケーションを有効に活かし、さらなる利用者の増加と本市の魅力を発信できる施設となるように在り方を見直します。また、今後の管理運営については、民間事業者の活力を積極的に活用できるような仕組みづくりを進めていきます。
分野別政策3 『くらし』を守る・快適にする
分野別政策3『くらし』を守る・快適にするための施策・事業として次のとおり進めてまいります。
<災害に強い地域づくりについて>
令和6年能登半島地震の発生や南海トラフ地震臨時情報の発出を踏まえ、地域のきずなの大切さや自主防災活動の重要性が改めて認識されており、自主防災組織等の育成、特に防災知識の普及啓発のための伝市メール講座の実施、自主防災組織が実施する訓練の支援などを行うとともに、次世代を担う小中学生の人材育成のため、学校が実施する防災教育を支援します。また、イオングループとの合同防災訓練の拡充を図るとともに、自助・共助の地域コミュニティーを基盤とした防災体制の確立に努めます。加えて、災害備蓄品の検証や避難所生活の質の向上を目指し、防災対策の強化を図ります。
<ため池の保全と活用について>
近年、局地的な大雨や大規模な地震の発生などで、ため池が決壊することによる水害が日本各地で発生しており、地域住民の皆様がもしもの災害発生時に迅速かつ的確な避難を行うことが可能となるよう、また、日頃の防災・減災意識の醸成のため、計画的にため池ハザードマップを作成します。
<防災体制の充実について>
防災情報の伝達につきましては、防災機能の強化を図るため、防災無線を更新し、防災無線と連動させた防災アプリの運用により情報伝達手段の多重化・多様化を図り、迅速かつ確実な情報伝達を実現させることで、市民の皆様や各種機関への周知・普及を推進します。
より効果的な災害対応を実現するため、各種団体との災害協定の締結を進めます。また、各種防災計画等の見直しや災害対策本部設置訓練等における実践的な訓練の追求により、具体的な災害対応が実施可能な体制の確立に努めます。
消防・救急体制につきましては、泉州南消防組合のスケールメリットと、これまでの消防活動における経験や知識を活かし、地元消防団との緊密な連携を図ることで、より確実かつ迅速な消防力を投入できるよう取り組みます。
<防犯対策について>
防犯対策につきましては、市民の皆様の安全・安心を確保するため、犯罪の抑止を目的として、150台を目標に防犯カメラを計画的に増設します。また、区等に対する防犯カメラ設置補助金の周知を図り、市内の防犯カメラの設置台数の増加を図ります。全国的に、多様化し、増加している特殊詐欺に対しては、広報紙や市ウェブサイトを通じた注意喚起を行うとともに、市内の65歳以上の高齢者の方を対象に、振り込め詐欺や還付金詐欺のような電話機を用いた特殊詐欺の被害を未然に防ぐため、引き続き、自動通話録音装置の貸与を行います。また、泉南警察署や防犯委員会など関係機関との連携による地域住民などへの啓発、青色防犯パトロール車による巡回をはじめ、地域との協働による防犯活動の推進に努めます。
<環境保全の促進・脱炭素社会の実現について>
近年、地球規模において、猛暑・豪雨・台風などによる甚大な気象災害が発生し、私たちの生命や暮らしが脅かされています。このような状況の中、「豊かな自然に包まれた、住み続けたいまち」を次世代にも引き継いでいくためには、市民・事業者・行政が一体となって脱炭素社会の実現を目指していくことが不可欠です。このことから、2050年までに二酸化炭素排出量をゼロにする「泉南市ゼロカーボンシティ」の実現に向けて取り組みます。
従来の3Rを推進しつつ脱炭素社会に向け、より環境への負荷が少ない2R(リデュース、リユース)の優先を明確にした施策の拡充を図ります。具体的には、廃棄物の減量、適正な処理に関する施策を総合的かつ計画的に推進します。
ごみ焼却施設につきましては、本年度、建て替えに関する基本協定の締結予定となっており、引き続き新炉建設に取り組みます。
<道路環境の整備について>
幹線道路の整備として、砂川樫井線の新家工区は早期供用開始に向けて工事の進捗を図ります。あわせて、市場長慶寺砂川線の狭小区間の拡幅工事や信達樽井線のバリアフリー化を目的とした歩道改修工事に取り組みます。既存の道路につきましては、地域道路網の安全性・信頼性を確保するため、橋梁法定点検の着実な実施、道路舗装や橋梁修繕の個別施設計画に基づく計画的な補修に取り組むとともに、グリーンベルトやカーブミラーなどの交通安全施設の設置を推進します。
また、樽井駅周辺地区においては、バリアフリー基本構想に基づく事業を検証し、道路などの施設のバリアフリー化を進めるため、基本構想の見直しを図ります。
<都市再生の推進について>
将来を見据え持続可能な都市構造への再構築を目指し、人口減少社会に対応したまちづくりを推進するため、都市計画マスタープランの高度化版として、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の考え方に基づき、立地適正化計画の策定に取り組みます。
<多様な交通手段の利用・導入促進について>
地域公共交通につきましては、市民の暮らしを支え、住みよい生活を営む上で公共交通は欠かせない存在である一方、人口減少や高齢化により公共交通を確保するための公的負担の増加等により、今後、その維持が厳しさを増すことが想定されます。これらを踏まえ、市民の皆様を交えたワークショップ等を通して、本市にとって「望ましい地域公共交通の姿」を把握し、地域公共交通計画の策定に取り組みます。
<広域ネットワークの構築について>
関西国際空港を核とした広域ネットワークにつきましては、空港へのアクセスの利便性や安全性の向上に向け、関係機関へ引き続き要望活動を行います。
また、海上空港という特性に起因するあらゆる危機、国際テロなどによる緊急対処事案に備え、リスクマネジメントの観点からアクセス方法に冗長性を持たせるため、関西国際空港連絡南ルートの実現に向けた要望活動を引き続き実施します。
<下水道の整備について>
下水道事業につきましては、ストックマネジメント計画に基づき、施設の維持管理と改築を効率的に実施します。特に、管渠の改築更新の交付金要件となっている、W-PPPの策定について検討していきます。2か所ある雨水ポンプ場については、長期的な計画の基、適切な時期に改築更新を実施します。また、将来にわたって安定した下水道運営を目指すため改定した泉南市下水道事業経営戦略に基づき、下水道使用料の改定について検討し、公共下水道の整備を推進します。
<公園について>
公園につきましては、泉南市都市公園等管理運営プランに基づき、効果的、効率的な管理運営手法を検討します。また、公園における犯罪の抑止等を目的として防犯カメラを設置し、安全・安心な公園づくりを推進します。
<住まいの提供について>
市営住宅につきましては、住民が安心して快適に居住できるよう、市営住宅長寿命化計画に基づき予防保全的な維持管理を計画的に実施し、市営住宅ストックの有効活用に努めます。また、未耐震住棟の早期解消を図るため、市営住宅建替事業において、前畑住宅の建替工事に着手します。
空き家対策につきましては、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、空き家の適正管理を促進するとともに、民間事業者団体とも連携し、空き家発生の未然防止及び特定空き家などの危険個所の除去や除却などの取組を強化します。また、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている危険な空き家を解体する所有者に対して、当該空き家を除却するための費用の一部を引き続き補助します。
加えて、危険な空き家を解体した所有者の空き家除却後の固定資産税などについて、除却後に高くなる税額分を引き続き減免します。
分野別政策4 『健幸』を築く・つながりをひろげる
分野別政策4『健幸』を築く・つながりをひろげるための施策・事業として次のとおり進めてまいります。
<安心できる医療環境づくり・健康づくりの推進について>
各種検診や生活習慣病発症予防、がん対策など、ライフステージに応じた健康増進に取り組み、市民の皆様の主体的な健康づくりを支援します。また、若年がん患者在宅療養支援事業の実施により、住み慣れた自宅で最後まで自分らしく安心して生活を送ることができるように、若年がん患者の方の在宅におけるターミナルケアの支援を行います。
国民健康保険につきましては、広域化により、安定的かつ持続可能な医療保険制度を目指していきます。本市においても医療費の適正化に努めるとともに、国民健康保険の健全な財政運営を確保するため、国や大阪府、また国民健康保険団体連合会と連携を図ります。後期高齢者医療保険につきましては、引き続き高齢者の保健事業と介護予防などの一体的な実施において高齢者の特性に応じた保健事業を行い、将来的な介護予防及び医療費の適正化につなげます。
<地域福祉・高齢者福祉・障害者福祉の充実について>
地域福祉の推進につきましては、高齢・障害・子育て・若者支援など、属性や世代を超え複合する課題にも柔軟に支援する体制の整備として、「泉南市版重層的支援体制整備事業」の令和8年度実施に向け、移行準備を進めます。
その中で、関係課や関係機関、事業者、地域を含め連携の一層の強化を図るとともに、地域福祉の充実を図り、課題を抱えた方が地域での生活を継続できるよう、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」、「受け手」という関係を超えて、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく地域共生社会を目指します。
高齢者福祉の充実につきましては、補聴器の活用により、今まで以上に、社会参加及び地域での交流を促し、認知症やフレイル予防につなげていくため、加齢等による聴力の低下により日常生活に支障のある高齢者の方に対して、補聴器購入費用補助制度を創設します。
認知症施策につきましては、もの忘れ検診を引き続き実施し、認知症の早期発見・早期診断を行うとともに、共生社会の実現を推進するため、「共に歩んでいく思いやりのまち泉南市認知症条例」を制定し、認知症の有無に関わらず、全世代が希望を持って安心して自分らしく暮らせるまちづくりを推進します。
障害者福祉の充実につきましては、相談支援体制の充実・強化として障害のある人の総合的な相談支援の中核的な機能を担う基幹相談支援センターを設置し、障害のある人やその家族が地域の中で安心して自分らしい生活を送ることができるよう、関係機関と連携し、引き続き、第7期泉南市障害福祉計画及び第3期泉南市障害児福祉計画に基づき、障害福祉サービスや障害児通所支援サービスなどの障害者福祉施策を進めます。
総合的政策『しくみ』をつくる・運営する
総合的政策『しくみ』をつくる・運営するための施策・事業として次のとおり進めてまいります。
<市民参画・協働の推進について>
市民参画・協働の推進につきましては、市民の皆様とともに考えるまちづくりを目指し、市政の現状や課題、施策等に関して市民と市長が直接情報交換を行う、タウンミーティングを開催します。また、市民の皆様の意見を市政に反映させるため、幅広いご意見をいただくための実施方法などを検討し、新たな市民参画・協働の仕組みづくりに取り組みます。
<シティプロモーションについて>
大阪・関西万博の開催や市制55周年にあたる本年を契機として、国内外からの誘客を図るため、様々な地域資源の磨き上げと活用に取り組みます。タルイサザンビーチと泉南ロングパークとを一体的に活用し、エリアとしての魅力をさらに高める取組や、ストーリー性のある地域資源の活用、また市民や市内事業者等の参画を得ることで、多彩な魅力発信を実現させ、積極的なプロモーションへとつなげていきます。
また、観光客の増加により本市の認知度を向上させ、企業の立地や投資を促進し経済活動が活性化することによって、税収が増加し、市民の皆様への還流を推進する好循環サイクルを目指します。さらに、現在策定を進めている「(仮称)泉南市公民連携推進によるまちづくり基本方針」に基づき、企業との連携を強化するためのプラットフォームの構築や事業者が市に対して提案を行うことができる「民間提案制度」を新たに設けます。これにより、これまで以上に企業との対話を進め、win-winの関係で連携し、民間の技術や知見を活用した地域活性化や社会課題の解決に向けた取組を進めます。
広報せんなんや各種SNSといった情報発信につきましては、市民の皆様に必要な情報を届けるだけでなく、市内外に本市の魅力の再発見や気づきがある情報提供に努めます。また、シビックプライドの醸成に繋がるよう創意工夫した発信に努めます。
<万博について>
本年4月には、いよいよ大阪・関西万博が開催されます。子どもたちが未来社会を体験することができる貴重な機会であり、未来を創る子どもたちの望ましい成長に寄与するものとして、学校単位での参加を支援します。本市としましても、万博会場で行われる各種催事への出展や市内での取組を通じて、シティプロモーションを推進します。具体的には、期間中3期にわたって開催される「大阪ウィーク 春・夏・秋」における、せんなんグルメの出展や本市観光大使のステージ出演、万博首長連合主催の「LOCAL JAPAN展」における健康・美・長寿の取組についての出展を万博会場で行います。
また、万博への送客と本市のプロモーションを目的とした本市内での万博関連イベントの開催、企業との協働による能登の子どもたちの万博招待と本市での子どもたちとの交流、フィリピン共和国や姉妹都市である同国ダバオ市との交流等を通じて、本市への集客・誘客や企業との連携を積極的に進めるとともに、関係機関と協力・連携して、同万博のレガシ―を見据えた地域活性化に向けた取組を推進します。
<情報政策(DX)について>
泉南市DX(デジタル・トランスフォーメーション)推進計画の目指す将来像「デジタルでつながる人とまち」に即した取組を進め、新しい地方経済・生活環境創生交付金などを活用し、誰もがデジタルの利便性を享受できる、市民の皆様にやさしいデジタル化に向けた取組を推進します。そのため、令和7年度についてはDX推進計画に沿い、現金だけでなく多様な支払い方法を利用可能とするキャッシュレス決済を拡充します。加えて、国が進める住民基本台帳や税に関するシステムなどのシステム標準化を進めます。
時代のニーズに即した施策の実現に向け、職員一人ひとりが意識を変え、従来のやり方にとらわれず、デジタル技術を用いてこれからの時代にふさわしい事業構築を図り、市民の皆様に寄り添った行政サービスの提供を目指します。
<組織の適正化と人材の育成について>
令和3年に内部統制制度を導入して以来、制度の定着、職員の意識改革等に取り組んできましたが、昨年、公金紛失等のリスク事案が発生し、マニュアルの再整備と周知徹底、会計事務研修の実施やセルフチェック機能の適切な運用などの再発防止に取り組んでいるところです。引き続き、リスク管理の徹底やリスク事案の共有により、財務事務の適正化を図り、ミスの起こりにくい組織づくりを進めます。また、包括外部監査につきましては、行財政に係る体制の整備と予算執行を見直す重要な機会と捉え、これまでの監査結果報告書を受けて必要な措置を講じるとともに、令和7年度以降も引き続き、第三者の視点による財務に関する監査を実施することで、市民サービスの向上や市政への信頼確保に努めます。
また、テレワークの導入、定着を進めるなど、すべての職員が、仕事と仕事以外の生活の両方を充実させる働き方ができる環境の整備を進めるとともに、名札の表記を変更し、職員の氏名が特定されSNS等でプライバシーが侵害されるなどの被害から職員を守る体制を構築することで、職員がその能力を十分に発揮でき、安全・安心な環境で勤務できる職場づくりに取り組みます。
また、官民問わず優秀な人材の獲得競争が激しくなる中で、持続可能な組織づくりと職員一人ひとりが高い意欲とやりがいを持って生き生きと働き続けられる職場環境の整備が重要です。そのため、昨日より今日、今日より明日、明日より未来の働き方改革を目的に、1年を通して、組織構造の見直しを検討するとともに、全庁的に働き方や職場環境の課題整理を行い、その解決に向けて働きやすい組織づくりを目指します。
また、人事院勧告の内容と本市の状況に即した給与制度についても検討するとともに、人事評価制度を活用した能力・実績に基づく昇給制度の運用に向けた制度の構築に取り組み、頑張る職員が適正に評価される人事給与制度改革を進めていきます。
広域連携による事務の共同処理につきましては、泉佐野市以南の3市3町の枠組みを基本に、地域の実情や事務処理の効率化を考慮し、積極的に取組を進めます。また、人口減少などに伴う行政課題を踏まえ、都市のあり方についても議論・研究を進めます。
<健全な財政運営について>
ふるさと納税につきましては、市内特産品の魅力を積極的かつ効果的に発信するとともに、ふるさと納税の周知に適したイベントに参加するなど、さらなる寄附の促進及びファンの獲得に努めます。
公共施設の再編につきましては、泉南市公共施設等最適化推進基本計画や個別施設計画などの改定に着手し、事業計画年度、立地エリア及び施設が担う機能を基に施設の複合化・集約化を含め、今後の再配置の具体案の策定及び事業化に向けた検討を進めます。それに加えて、公共施設跡地に関しましては、庁内の統一的な活用方針などを策定・運用することにより、効率的かつ効果的な活用などを図ります。また、(仮称)西信達義務教育学校建設に伴う西信達小学校の跡地につきましては、関係機関や庁内関係部局と連携しながら、民間活力導入を検討するとともに、地域ニーズを踏まえた有効活用の取組を引き続き進めます。
財政運営につきましては、人口減少や少子高齢化、公共施設の老朽化、また物価高騰に伴う行政コストの増大や国際情勢など、本市を取り巻く課題や環境は厳しさを増しており、引き続き中長期的な視点に立った財政シミュレーションに基づき、財政運営の計画性と透明性を確保し、将来負担をしっかりと踏まえた予算編成の基、将来にわたり持続可能な財政運営を確立します。
歳入の根幹である市税収入につきましては、安定的な財政基盤の確立のため、引き続き適正で公平な課税及び徴収を行うとともに、高い専門性が求められる税務事務に従事する職員の育成に取り組み、貴重な自主財源の確保に努めます。
結び
以上、私の所信と令和7年度の市政運営の基本方針につきまして、ご説明いたしました。
ただし、政策を実行していくことは、当然、私一人でできるものではありません。これらの施策は、市民の皆様との協働によってのみ実現可能です。これからも、市民の皆様と対話しながら、そこでいただいた市民の皆様の声を大切にし、職員とともに知恵を絞りながら市民の皆様からの学びを積極的に市政運営に活かしてまいります。
引き続き、市民の皆様や市議会の皆様、職員の皆様のご理解とご協力を賜りますよう、心からお願い申し上げます。
令和7年度市政運営方針 (PDFファイル: 721.5KB)
令和6年度市政運営方針 (PDFファイル: 475.2KB)
令和5年度市政運営方針 (PDFファイル: 603.1KB)
令和4年度市政運営方針 (PDFファイル: 778.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
政策推進課
政策推進係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-0004
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:seisaku@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから