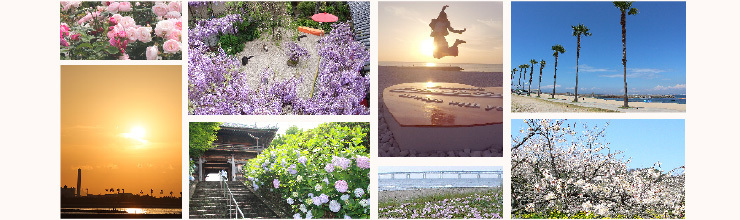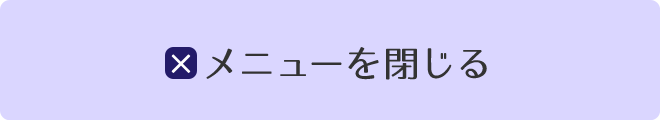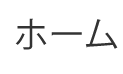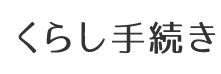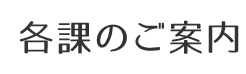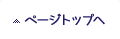重要文化財-相輪-
相輪(そうりん)
相輪に吊るされたベル【相輪風鐸(そうりんふうたく)】

五重塔の頂上には金色に輝く相輪(そうりん)が飾られていました。相輪部分だけでも高さ10メートルを超え、当時の最新技術を結集することでつくられていました。
この相輪風鐸(ふうたく)は、相輪のうち九輪(くりん)や水煙(すいえん)にぶら下げられていたもので、今もなお1350年前の輝きを放(はな)っています。
高さ17センチ/7世紀後半
相輪の部品【水煙・九輪など(すいえん・くりん)】

五重塔倒壊(とうかい)の衝撃(しょうげき)によって粉々に割れていますが、相輪を構成するあらゆる部品が見つかっています。
右下長さ16センチ/7世紀後半
銅でできた相輪の部品【銅製露盤(どうせいろばん)】

銅でできた厚さ2センチ程の板状の製品で、復元すると一辺が1.5メートルの方形になります。下の凝灰岩(ぎょうかいがん)製露盤(ろばん)と組み合わさって相輪の基台部分を構成していました。このように石と金属を組み合わせた構造の露盤は、他の古代寺院では見つかっておらず、非常に特殊なものです。
復元長1.5メートル/7世紀後半
石でできた相輪の部品【凝灰岩製露盤(ぎょうかいがんせいろばん)】

露盤とは相輪の根元、基台部分にあたります。奈良県との県境にある二上山(にじょうざん)から運ばれてきた凝灰岩でできています。
復元長1.5メートル・高さ40センチ/7世紀後半
このように海会寺跡からは相輪を構成するあらゆる部品が見つかりました。これらを忠実に再現した復元模型が埋蔵文化財センターに展示されています。
風鐸(ふうたく)
軒先に吊るされたベル【風鐸(ふうたく)】
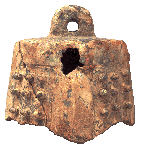
堂塔の軒先に吊り下げられたもので、乳(にゅう)と呼ばれる小さな突起がたくさんつけられています。本来は金色に輝いて荘厳な音色を響かせていたものでしょう。
高さ14センチ/7世紀後半
ベルの打棒【風鐸の舌(ぜつ)】

風鐸の内部に吊るされた打棒(だぼう)です。本来はさらに風招(ふうしょう)という板がつき、風を受け音を奏(かな)でていました。
長さ25センチ/7世紀後半
この記事に関するお問い合わせ先
泉南市埋蔵文化財センター
〒590-0505大阪府泉南市信達大苗代374番地の4
電話番号:072-483-6789
ファックス番号:072-483-7306
e-mail:maibun@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから