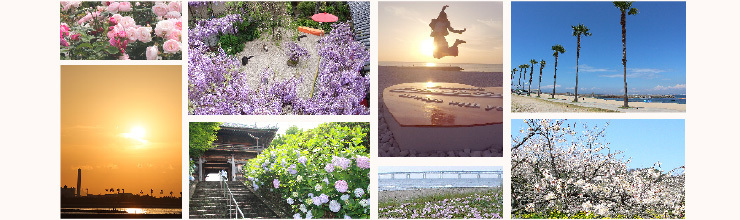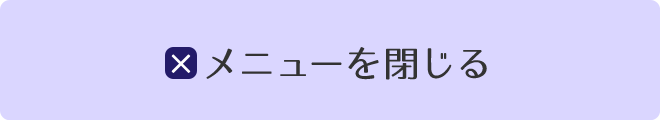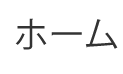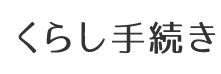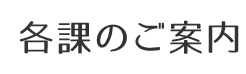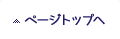市税についてのQ&A
市税についてのQ&A
目次
Q5.昨年亡くなった方の今年度の住民税は、どうなるのですか?
Q6.1月1日現在に日本国内に住所がない方に支払われる退職所得に対する住民税は?
市税についてのQ&A
住民税と所得税の違いは?
Q1.住民税と所得税の違いは?
私はサラリーマンです。毎月の給与からは住民税と所得税が引かれていますが、そもそも住民税と所得税とはどんなところが違いますか?
A1.所得にかかるという点では、住民税(市町村民税と道府県民税をあわせて住民税と呼んでいます。)も所得税も同じですが、両者の主な違いには次のようなものがあります。
地方税と国税
住民税は市町村あるいは道府県が課税する地方税の1つです。一方所得税は国が課税する国税の1つです。
前年所得課税と現年所得課税
住民税は令和6年中(令和6年1月から令和6年12月)の所得に対して、令和7年度に課税しますが、所得税では令和6年中の所得は令和6年中に課税されます。所得税に年末調整があって、住民税にないのはこのためです。
均等割の有無
住民税には、所得額にかかわらず一定額を課税する均等割と所得額に応じて課税する所得割がありますが、所得税には均等割にあたるものがありません。
その他
申告すべき所得額の範囲、所得控除における各種控除額、あるいは適用される税率などが住民税と所得税では異なっています。
確定申告と住民税の申告は?
Q2.確定申告と住民税の申告は?
私は個人で事業を営んでいますが、税務署へ確定申告に行くと、所得税がかからないので確定申告の必要がないと言われました。この場合、住民税の申告も必要ないのでしょうか?
A2.税務署への確定申告が必要でない場合でも、前年中に所得があれば、住民税の申告をしていただく必要があります。なお、前年が失業などでまったく所得がない場合は申告の必要がありませんが、保育所入所、就学援助金、公営住宅入居等の申請のとき、課税(所得)証明書が必要な場合は、「所得なし」の旨の申告を行ってください。
子どもが生まれたら?
Q3.子どもが生まれたら?
私の子どもは、昨年の12月28日に生まれました、友人にも今年1月3日に子どもが生まれました。どちらも年末調整で子どもの扶養控除の申請が間に合いませんでした。このような場合、扶養控除の申請はどうすればよいのでしょうか?
A3.扶養親族の認定は昨年の12月31日現在で判定します。あなたの場合は、お子さんが昨年生まれていますので、もう一度勤務先で年末調整をやり直してもらうか、ご自身で税務署に確定申告することにより、扶養を反映することが可能です。しかし友人の場合は、お子さんが生まれたのが今年に入ってからですので、昨年の年末調整の扶養控除の対象とはなりません。
(注意)平成24年度から、扶養控除の見直しが行われ、16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されました。したがって、所得金額及びその他の所得控除額等に変更がなければ、16歳未満の方を扶養親族として申告されても所得税、市・府民税額は変わりません。
ただし、市・府民税の非課税限度額を算定する際には、16歳未満の年少扶養親族も含めることができます。
学生、未成年者の場合も税金を払わないといけない?
Q4.学生、未成年者の場合も税金は払わないといけない?
私は学生でアルバイトをしているのですが、税金を払わないといけないですか?
A4.学生、未成年の方であっても、所得が一定以上あれば所得税、市・府民税が課税されます。
非課税の要件については、扶養親族がいない場合、前年中の合計所得金額が42万円(給与収入のみの場合97万円)以下の場合で、それを超えると市・府民税の均等割が課税され、45万円(給与収入のみの場合100万円)を超えるとさらに市・府民税の所得割が課税されます。
ただし、前年中の合計所得金額が75万円(給与収入のみの場合130万円)以下で、勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下の場合、勤労学生控除を申告すれば、市・府民税で26万円の所得控除を受けることができます。(詳しい要件は、下記外部リンクをご覧ください。)
未成年者の場合
民法の改正に伴い、令和4年4月1日から、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。賦課期日(その年の1月1日時点)現在で18歳未満(令和7年度の場合は、平成19年1月3日以降に生まれた方)の方が未成年者に該当します。
未成年者の非課税基準は、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入のみの場合204万4千円未満)です。
ただし、合計所得金額が48万円(給与収入のみの場合103万円)を超えると、親などの税の扶養に入っている場合、扶養から外れてしまうため注意が必要です。
(注意)
・扶養親族がいる場合等は、市・府民税が課税されない前年中の合計所得金額の範囲が異なります。
昨年亡くなった方の今年度の住民税は、どうなるのですか?
Q5.昨年亡くなった方の今年度の住民税は、どうなるのですか?
私の夫は、昨年、死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対する住民税はどうなるのでしょうか?
A5.住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。したがって、昨年中に死亡された方に対しては、今年度の住民税は課税されません。
なお、あなたが扶養している方が亡くなられた場合は、12月31日現在の扶養状況でなく、その死亡時点での扶養状況によって判定するため、年の途中で死亡しても、その年分の所得については扶養控除が認められます。
1月1日現在に日本国内に住所がない方に支払われる退職所得に対する住民税は?
Q6.1月1日現在に日本国内に住所がない方に支払われる退職所得に対する住民税は?
S社に勤務する社員Aは、令和4年4月に3年間の海外勤務のため出国し、令和7年5月に帰国し、この7月に会社を定年退職する予定です。その際Aに支払われる退職所得に対する住民税の徴収はどのようにすればよいのでしょうか?
A6. 市町村内に住所を有する人が退職金の支払いを受ける場合における退職所得に対する住民税については、原則として、退職金の支払いをする者がその支払いをする際に他の所得と区分して徴収し、納税義務者のその年の1月1日現在の住所所在の市町村に納入することとされています。
したがって、貴社のAさんは、国内において退職金の支払いを受けたとしても、退職金の支払いを受けた日の属する年の1月1日現在において外国に居住していたことにより国内に住所を有していないことから、分離課税の対象となる退職所得に対する住民税の納税義務はなく、貴社は、Aさんに対して退職金を支払う際に退職所得に対する住民税を特別徴収する必要はないこととなります。
なお、Aさんの退職所得については、Aさんが令和7年の1月1日現在において国内に住所を有する場合には、他の所得と同様に令和7年度の住民税が課税されることとなります。
年の途中で引っ越した場合に住民税を納める市町村は?
Q7.年の途中で引っ越した場合に住民税を納める市町村は?
私は令和7年1月10日に泉南市から他市へ引っ越しました。令和7年度の住民税はどちらへ納めることになるのでしょうか?
A7.令和7年1月1日現在ではあなたの住所は泉南市にあったのですから、その後他市に引っ越したとしても、令和7年度の住民税は泉南市に納めていただくことになります。
昨年海外へ転勤した場合の住民税は?
Q8.昨年海外へ転勤した場合の住民税は?
私はS社に勤務し泉南市の独身寮に住んでいましたが、令和6年10月1日付けで2年間外国に転勤することとなり、同日に出国しましたが、令和7年度も住民税が課税されるのでしようか?
A8.日本国内に居住していた人が、出国により1月1日現在において、国内に住所を有しない場合及びその人が1月1日現在において国内に事務所、事業所又は家屋敷を有しない場合は、個人の住民税の納税義務はないものとされております。
ただし、法施行地に住所を有しないかどうかは、実質的に判断するものとされており、たまたま1月1日現在出国していた人でも、その人の出国の期間、目的、出国中の居住の状況等から単に旅行にすぎないと判断される場合には、出国前に居住していたところに住所があるものとして取り扱われることになります。また1月1日現在その人が、国内に住所を有するかどうか明らかでない人については、
・その人が日本国外において、継続して1年以上居住することを必要とする職業を有している場合
・その人が日本国籍を有してなく外国の法令により永住権を受けている場合でその人との資産の状況等から出国後1年以内に再び日本国内に居住することはないと認められる場合
のいずれかに該当すれば、日本国内に住所を有しないものとして取り扱われることとなります。したがって、あなたの場合は、令和7年1月1日現在、日本を出国しており、また、2年間の海外勤務のため1年以内に再び国内に居住するとは考えられませんので、国内に住所を有しないことから令和7年度の住民税は課税されません。
給与所得以外の所得が20万円以下の場合の住民税の申告は?
Q9.給与所得以外の所得が20万円以下の場合の住民税の申告は?
私は勤務のかたわら仕事関係の雑誌に原稿を書き、その所得が15万円ほどあります。所得税の場合は20万円以下であれば申告不要と聞いておりますが、住民税の申告はする必要がありますか?
A9.所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされておりますが、住民税においては、このような源泉徴収制度がなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず申告しなければなりません。
サラリーマンの年末調整とは?
Q10.サラリーマンの年末調整とは?
サラリーマンの年末調整という言葉をよく聞きますが、年末調整とは何でしょうか?
A 10.年末調整とは、サラリーマンの方の「所得税の清算」作業のことです。所得税は、本来その年の年間所得金額をもとに算出するのですが、サラリーマンの場合、毎月の給与等から概算で所得税を天引きしています。その1年間の納税額と年間所得金額をもとに算出した本来納税すべき税額を清算します。したがって、このときに勤務先が本人に代わって所得税を清算していますので、他に所得がなければ、申告の必要はありません。しかし、 雑損控除・医療費控除・寄付金控除などは年末調整では受けられませんので、確定申告を行う必要があります。
サラリーマンで確定申告が必要な場合
・年間2,000万円を超える給与収入がある人
・給与以外に不動産所得や事業所得がある人
・2か所以上から給与をもらっている人
・副収入の所得金額が20万円を超える人
・一般口座など、源泉徴収なしで株取引した人
・贈与を受けた人
など
所得税が戻ってくる場合は?
Q11.所得税が戻ってくる場合は?
所得税の確定申告をすると、税金が還付されることがあるそうですが、どのようなときですか?
A11.所得税を毎月の給料から天引き(源泉徴収)されて納税し、12月に年末調整が済んでいる場合でも、次のようなことがあると、税務署へ所得税の確定申告をすると還付される場合があります。
・災害や盗難などによって資産に損失をうけた ⇒ 雑損控除
・病気や出産などで多額の医療費を支払った ⇒ 医療費控除
・自分が住むために、金融機関等からの借入金によって新築住宅等を取得したり増改築を行った ⇒ 住宅借入金等特別税額控除
・国や地方公共団体などに寄付をした ⇒ 寄付金税額控除
また、年末調整の後で、扶養控除に変更(増える場合)があったり、勤務先に提出していなかった生命保険や地震保険などの支払い保険料の額を証明する書類があった場合などは、勤務先で年末調整の再調整や確定申告をすることによって還付を受けられることがあります。
なお、詳しいことは所管の税務署へお問い合わせください。
(泉南市にお住まいの場合、泉佐野税務署(電話番号:072-462-3471)がお問い合わせ先になります。)
住民税については、所得があった年の翌年に税額を計算しますので、通常還付はありません。
退職したときの住民税は?
Q12.退職したときの住民税は?
私は、退職するのですが、今まで給与から住民税を天引きされていました。来年5月分まで毎月天引きされると聞いていましたが、残りの住民税はどんな方法で納めるのですか?
A12.住民税は、1年間の税額を12回に分けて毎年6月から翌年の5月までの毎月の給与から差し引かれます。この間に退職すると、退職してから翌年5月までの市・府民税の納税通知書が市から送られてきますので、これで納めます。(ただし、翌年の1月1日から4月30日までに退職した人で、残りの税額を超える退職手当等がある場合は、申出がなくても退職手当等から残りの税額を一括徴収します。)また、希望すれば、退職金などから一括で翌年の5月までの住民税を差し引いたり、再就職した会社の給与から引き続き差し引いたりすることもできます。
市役所発行の税証明は?
Q13.市役所発行の税証明は?
いろいろな申請書類の説明書に、市役所発行の「税証明を添付」とよく書いてありますが、税証明とはどのようなものでしょうか?
A13.市が発行する「税証明」の主なものとしては、下表のような証明があります。これらの証明のうち「どの証明が必要か?(どんな内容の証明か)」は、使用目的によって異なります。たとえば、融資の場合、「1年間の所得がいくらあったか?」がわかる『市・府民税課税(所得)証明』、保証人の場合には、「市・府民税をいくら課税され、いくら納めているか?」がわかる、『市・府民税納税証明』、が必要というように、それぞれに異なる場合があります。また、市税は毎年度新たに課税されるため、「いつの年度に課税された証明」が必要であるかも大切です。証明を請求する前に、必ず「だれの ?」「いつの年度に課税された?」「どんな内容?」「どこに提出?」の税証明が必要なのかを確認してください。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 市・府民税課税(所得)証明書 | 1年間(1月1日〜12月31日)の所得金額と税額など |
| 固定資産評価証明書 | 土地・建物の所在地、地積、床面積とその評価額など |
| 固定資産公課証明書 | 「評価証明」の内容に加えて、課税標準額と税額 |
| (各税)の納税証明書 | 市・府民税、固定資産税、その他の市税の課税額と納付額など |
親の所得証明もすぐにもらえますか?
Q14.親の所得証明もすぐにもらえますか?
母から、所得証明を取りにいってほしいと頼まれました。私が、母の所得証明を請求することはできますか?
A14.税証明の内容は、プライバシーにかかわることであり、プライバシーの保護は税務の仕事を進めていく上で非常に重要なことです。このため税証明を請求される方は、一定の条件を満たす必要があり、確認のための書類などの提示、提出をお願いしています。
あなたが現在、母親と同一世帯の場合には、母親から請求に関して同意があったものとして、課税(所得)証明書を交付します。一方、同一世帯ではない場合は、あなたとの関係が明白ではなく、同意があったかどうかも判断できません。同一世帯ではない場合または別居している場合には、母親からの委任状を添えて請求していただければ、課税(所得)証明書を交付します。
委任状は委任者(この場合は母親)が自署してください。あなた(受任者)の名前、住所、使用目的、証明書の種類、母親(委任者)の住所・氏名を明記し押印が必要です。
|
委任状(中央ぞろえに) |
委任状の書き方 (1)代理人の氏名、住所 (2)使用目的 (融資、保証人、扶養、住宅など) (3)課税の年度 (4)証明書の種類 (5)必要な枚数 (6)依頼人の住所と氏名 |
・年度分か年分か?
税務課の窓口でよく悩まれるのが「年度分か年分か」ということです。たとえば、令和7年度の所得・課税証明には令和6年中の所得に対して課税された令和7年度の住民税が記載されています。単に「令和6年の証明を」と請求があっても、令和6年度の課税証明か令和6年分の所得証明かの判断がつきかねない場合もありますので、提出先などで確認し、請求してください。
原付を廃車したのに、納税通知書が?
Q15.原付を廃車したのに、納税通知書が?
私は、原付(原動機付自転車)を今年の4月下旬に廃車しました。ところが5月に納税通知書が送られてきました。廃車したのに、どうして納税通知書が送られてきたのでしょうか?
A15.軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者に対して課税されます。あなたの場合、原付の廃車が4月下旬ですので、今年の4月1日現在では、原付を所有していたことになります。したがって、納税通知書が送付されてきたのです。なお、軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありません。
原付の届出は?
Q16.原付の届出は?
私は、最近泉南市に転入してきました。原動機付自転車(原付)のナンバープレートは前に住んでいた市役所で交付を受けたものですが、そのまま乗っていてもいいのでしょうか?
A16.原動機付自転車(原付)は、その主たる定置場の市町村で課税されます。転出入によってその主たる定置場が変わった場合には、まず、以前住んでいた市町村でいったん廃車の手続きをしてナンバープレートを返却します。次に泉南市で、登録の手続きをしてナンバープレートの交付を受けることになります。
主たる定置場とは…
- 原動機付自転車や小型特殊自動車
A.所有者が個人である場合は、その住所地
B.所有者が法人である場合は、その車両を使用する事務所の所在地 - 軽自動車や二輪の小型自動車
A .軽自動車使用届出済証または自動車検査証を交付された場合は、その使用届出済証 または自動車検査証に記載された使用の本拠地
B. A以外の場合は、その所有者の住所地
この記事に関するお問い合わせ先
課税係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:(市民税)072-483-9031または(固定資産税)072-483-9032
ファックス番号:072-483-0325
e-mail:kazei@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから