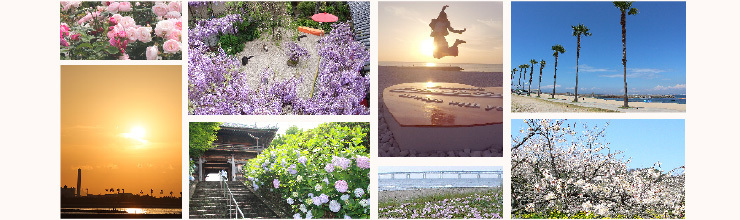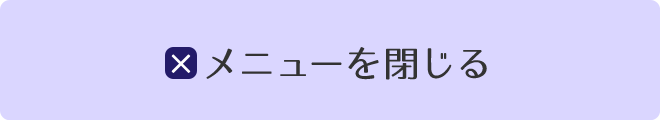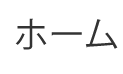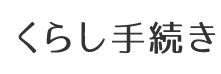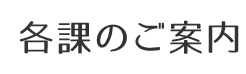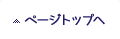なぜ子どもの権利救済委員会ができたの?
泉南市子どもの権利に関する条例(2025年3月改正)
2012(平成24)年10月に「泉南市子どもの権利に関する条例」が制定されました。
1. 準備委員会の設置(2019年)
相談救済のための公的第三者機関の必要性については、「泉南市子どもの権利に関する条例」の条例委員会の2014(平成26)年第2次市長報告より、継続的に提言をいただいており、2018(平成30)年の第6次市長報告においては、「泉南市モデル」の設計に向けての考え方が示されました。
それらの提言を受け、2019(令和元)年7月、泉南市公的第三者機関の創設に向け、関係部署による準備委員会を設置し、検討を始めました。
2. 子どもの権利を基盤としたネットワークづくり(2020~2024年)
準備委員会が設置された翌年の2020(令和2)年から2024(令和6)年の5年間は、公的第三者機関の設置に向けて、職員および市民向け研修を実施しました。
市民向け研修は、子どものことを「You are important to me(あなたはとても大切な存在)」と尊重し、子どもの権利を基盤に子どもの話を聴き、寄り添うおとな「ゆうてみぃサポーター」を、子どもが成長する身近な地域に増やそうと、連続研修を実施しました。また、行政職員や教職員を対象とした研修、子ども向けの教材研究等、子どもの権利の広報啓発に力を入れ、引き続き、子どもの権利を理解するための研修を継続し、子どもの権利を基盤としたまちの基礎となる人の輪を広げていきました。
3. 子どもの権利に関する本部会議・専門部会の設置(2024年)
準備委員会において、公的第三者機関を検討している最中の2022(令和4)年3月に、市内中学生が自死するという事案が起こり、再び尊い命がなくなることのないよう、2024(令和6)年4月にこれまでの準備委員会を「相談・救済機関設置にむけた専門部会」と変更し、子どもが悲しい、苦しい、辛い時などに寄り添い、行動し、救済することのできる救済機関の設置に向けての検討を重ねました。
4. 条例委員会の提言(2021~2024年)
その間、条例委員会からは2021(令和3)年11月の第9次市長報告において、公的第三者機関の試行的な全体構造の骨格が示され、2022(令和4)年8月には第10次市長報告として、条例委員会に救済委員会の役割を付加する案が示されました。
その後、第13次市長報告(第1回)として2024(令和6)年7月に「子どもの人権機関の制度設計に必要な条例改正等に関する提言」、また10月に第13次市長報告(第2回)として具体的な条例改正案が示されました。
5. 条例の改正(2025年)
相談・救済機関設置にむけた専門部会では、これらの提案をもとに検討をすすめ、条例案を作成し、パブリックコメントを募集したのち議会に諮り、2025(令和7)年第1回議会において改正条例案が可決されました。
改正条例から見る救済委員会の役割と機能
条例第15条
|
1 市長及び教育委員会は共同して、泉南市のすべての子どもの尊厳と権利が不断に尊重され、及び擁護され、救済される「まちづくり」を改めて推進するため、第6条第2項に基づいて、子どもの権利に関する識見を持つ有識者等で構成する、子どもの権利救済委員会(以下「救済委員会」といいます。)を設けます。
2 市民等は、子どもであるかおとなであるかを問わず何人も、第3条に規定する「子どもの権利の尊重」に基づき、子どもの権利が侵害されている疑いがもたれるとき、第6条第1項に規定する子どもの権利に根差して救済委員会に相談し、又は救済の申立てを行うことができます。
3 救済委員会は、自らを子どもの権利の擁護者、代弁者、そして公的良心の喚起者として深く認識し、その職務の遂行に努めなければなりません。 |
泉南市が「子どもに(とって)やさしいまち」になっていくよう、まず子どもの思いや意見を受け止めます。
そして必要ならば「調整」や「調査」を行って子どもの代弁に努め、どうすれば子どもの最善の利益を実現できるかを、子どもと一緒に考え行動します。
条例第16条
|
1 救済委員会は、第3条に規定する「子どもの権利の尊重」が具体的に実現されるよう、次に掲げる事項を自らの職務として担います。 (1) 前条第2項に基づく相談及び救済の申立てを受けること。 (2) 前号の救済の申立てを受け、又は自己の発意により、必要な調査を市及び子ども施設に対して行うこと。 (3) 調査の結果、必要と認めるときは、是正措置の勧告、制度改善の要請、その他意見表明を行うこと。 (4) 前号を受けて講じた措置について、報告を求めること。 (5) 前各号の内容について、必要と認めるときは、その内容を公表すること。 (6) 子どもの権利に対する人権侵害の予防的活動として、広報及び啓発を行うこと。
2 救済委員会は、第19条第2項の子どもの権利条例委員会が行う検証及び報告等に資するため、子どもの権利条例委員会に協力するよう努めます。
3 救済委員会は、第1項に関する活動の総括等を行い、これについて原則として年次的に、市長及び教育委員会に報告し、市民等に公表します。 |
子どもの権利救済委員会は、行政や学校や保護者からは独立した立場で、子どもの権利を基盤として子どもの最善の利益を追求する機関です。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども政策課
子ども政策係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-447-7747
ファックス番号:072-483-7667
e-mail:kodomo@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから