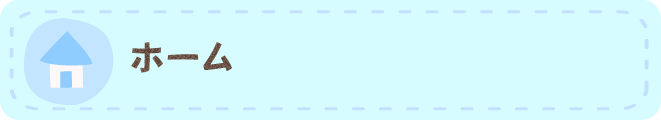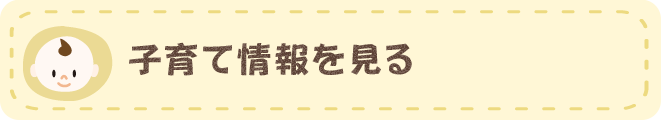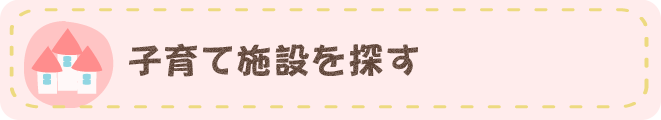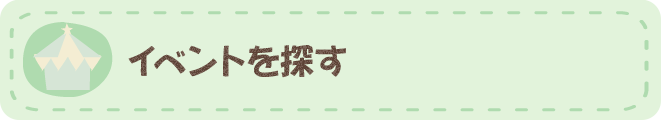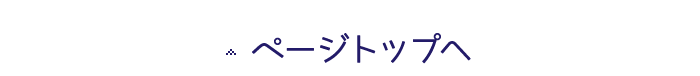児童手当
お知らせ
【2月期分(12月分・1月分)の児童手当支給について】
令和8年2月13日(金曜日)に支給します。
児童手当制度の改正に伴い、支払通知書の送付は廃止されましたので通帳の記帳によりご確認ください。
【現況届のお知らせ】
原則提出不要ですが、一部提出が必要な方がいます。
(今年度より「大学生年代」となる子についても一部現況届の提出が必要となっています。)
提出が必要な方には、現況届を郵送します。
現況届が届いた場合は必要事項を記入のうえ、提出してください。
提出期限は6月30日(月曜日)です。
届出がない場合は、6月以降の手当てが支給されませんのでご注意ください。
児童手当制度改正について
・児童手当については、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、国による制度改正が行われます。
・制度改正についてはこちらのページをご覧ください。
児童手当制度の概要
児童手当は家庭における生活の安定と、これからの社会を担う子どもの健やかな成長のために、18歳到達後の最初の年度末までの子どもを養育している方に支給する手当です。
対象児童
日本国内に住所を有する高校生年代(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)の児童
(注意)海外に居住する子どもは、留学中の場合を除き、手当の支給対象となりません。
(注意)児童福祉施設等に入所(2か月以内の短期入所や通所を除く)している子ども又は里親等に委託(2か月以内の短期委託を除く)されている子どもは、手当の支給対象となりません。
受給者(請求者)
泉南市に住所を有し、高校生年代以下(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)の児童を養育している方。
(注意)児童を養育している父母等のうち、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が受給者(請求者)となります。(支給開始月が1~5月の場合は前々年の所得、6~12月の場合は前年の所得を基準とします。)
(注意)公務員の方は原則職場での手続きとなります。ただし、独立行政法人等にお勤めで、勤務先から支給されない場合は居住している自治体に申請が必要です。
支給額
対象となる児童1人あたり年齢に応じて下記の金額が支給されます。
| 区分 | 児童1人当たりの月額 |
| 3歳未満(第1子・第2子) | 15,000円 |
| 3歳未満(第3子以降) | 30,000円 |
| 3歳~高校生年代(第1子・第2子) | 10,000円 |
| 3歳~高校生年代(第3子以降) | 30,000円 |
(注意)第1子、第2子などの数え方は、22歳に達する日以後最初の3月31日までに間にある子どもを、年齢が上の子どもから順に数えます。
(注意)施設に入所している子どもは第1子、第2子などを数える対象となりません。
(注意)第1子、第2子などの数える対象となる子は、手当受給者又は手当請求者の経済的負担がある場合に限る
所得の種類
| 総所得 |
| 退職所得 |
| 山林所得 |
| 土地等に係る事業所得等 |
| 長期・短期譲渡所得(分離課税) |
| 先物取引に係る雑所得等 |
| 特例適用利子等・特例適用配当等 |
| 条約適用利子等・条約適用配当等 |
(注意)給与所得または公的年金所得がある場合、総所得金額から上限10万円を控除します。
控除の種類及び控除額
| 控除の種類 | 控除額 |
| 雑損控除 | 控除相当額 |
| 医療費控除 | 控除相当額 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 |
| 障害者控除(特別障害者控除) | 27万円(40万円) |
| 寡婦控除 | 27万円 |
| ひとり親控除 | 35万円 |
| 勤労学生控除 | 27万円 |
支給月
| 支払日 | 支払対象月 |
| 4月15日 | 2,3月分 |
| 6月15日 | 4,5月分 |
| 8月15日 | 6,7月分 |
| 10月15日 | 8,9月分 |
| 12月15日 | 10,11月分 |
| 2月15日 | 12,1月分 |
(注意)振込日が休日等に当たる場合は、その直前の休日等でない日に振り込みます。
手続きに関すること
申請・届出方法
家庭支援課子ども給付係㉖の窓口へお越しください。
ご来庁が難しい場合は、郵送での申請・届出も受け付けています。
郵送の場合は、書類が市役所に届いた日を申請・届出日として取り扱います。
また、一部手続きについては、電子申請での申請・届出も受け付けています。電子申請を行う場合は個人番号カード(マイナンバーカード)が必要です。電子申請可能な手続きは下記記載の手続きです。






(注)電子申請利用方法についてはこちら。
(注)マイナンバーカード読取対応のスマートフォン又はICカードリーダライタが必要です。詳しくはこちら。
出生・転入の場合
申請期限
原則申請日の翌月分から受給資格が発生します。
月末に出生・転入された方は出生日・前住所地で転出手続きをした際の転出予定日の翌日を起算として、15日以内に申請すれば、当該出生日・転出予定日の翌月分から支給されます。
お早めに手続きください。必要書類がそろわない場合は、先に認定請求書と提出できる書類で申請手続きをお願いします。
必要なもの
第1子が生まれた方・転入してきた方
(注意)公務員の方が退職又は独立行政法人等に派遣された時も同様
児童手当認定請求書(記入例)(PDFファイル:430.7KB)
(注意)18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童手当支給対象児童の兄姉等がいて、その児童の兄姉等について、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしかつその生計費を負担している場合で、児童手当支給対象児童と併せて3人以上となる場合は以下の確認書の提出が必要です。
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:92KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDFファイル:112.6KB)
本人確認書類(注1)
請求者名義の通帳等(銀行名・支店名・口座番号がわかるもの)
請求者の医療保険の加入関係を確認できるもの(「健康保険証」、医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」若しくは「資格確認書」、マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」の写し、のうちいずれか1点)((注2)
請求者・配偶者の個人番号確認書類(注3)
第2子以降が生まれた方
児童手当額改定請求書(記入例)(PDFファイル:397KB)
本人確認書類(注1)
請求者の医療保険の加入関係を確認できるもの(「健康保険証」、医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」若しくは「資格確認書」、マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」の写し、のうちいずれか1点)(注2)
(注1)次のうち有効期限内のもの
いずれか1点の提示
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳 など公的機関発行の顔写真付き身分証明書類
いずれか2点以上の提示
各種健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等
(注2)以下の場合以外は年金加入証明書に勤務先から証明をもらいご提出ください
請求者(受給者)が被用者年金(厚生年金・共済年金など)に加入しており、健康保険証の種類が次のいずれかである。
健康保険被保険者証(健康保険組合、全国健康保険協会)
船員保険被保険者証
私立学校職員共済加入者証
全国土木建築健康保険組合員証
日本郵政共済組合員証
文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかなもの
(注3)次のうち有効期限内のもの
個人番号カード
通知カード
個人番号が記載された住民票の写し
住民票上請求者(受給者)と児童が別居している方
単身赴任等で請求者(受給者)と児童が別居している場合、通常必要なもののほかに以下が必要です。
別居している児童の個人番号確認書類(注3)
転出の場合
転出される月(転出予定日の属する月)までの手当が泉南市から支給されます。
転出の際は以下の書類を提出してください
受給者が公務員になった場合
本市への消滅届出と勤務先での認定請求を行ってください。
受給者が公務員でなくなった場合
本市への認定請求と勤務先での消滅届出を行ってください。
子どもが児童福祉施設等へ入所したとき又は里親等へ委託されたとき
2か月以内の期間を定めて施設入所又は里親に委託されている場合は手続不要です。
振込先口座を変更したい場合
ご指定いただける口座は、受給者本人の口座に限ります。
受給者又は児童の住所又は氏名に変更があった場合
以下の書類を提出してください
受給者の加入している年金に変更があった場合(3歳未満の児童を養育している場合のみ)
以下の書類を提出してください
受給者の医療保険の加入関係を確認できるもの(「健康保険証」、医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」若しくは「資格確認書」、マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」の写し、のうちいずれか1点)
(注意)以下の場合以外は年金加入証明書に勤務先から証明をもらいご提出ください
請求者(受給者)が被用者年金(厚生年金・共済年金など)に加入しており、健康保険証の種類が次のいずれかである。
健康保険被保険者証(健康保険組合、全国健康保険協会)
船員保険被保険者証
私立学校職員共済加入者証
全国土木建築健康保険組合員証
日本郵政共済組合員証
文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかなもの
受給者が婚姻により配偶者を有するに至った場合又は離婚により配偶者がいなくなった場合
単身赴任等により子どもと別居している場合
受給者となる方が、単身赴任等により子どもと別居している場合は、受給者となる方のお住いの市区町村での申請が必要です。
本市で受給される場合は以下の書類が必要です。
別居している児童の個人番号確認書類(注3)
未成年後見人が児童を養育している場合
児童が留学により日本国内に居住していない場合
留学とは次の要件をすべて満たすものです。
1.日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本に継続して3年を超えて住所を有していたこと
2.教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母等と同居していないこと
3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること
(注意)支給対象児童の兄姉等として、第3子以降カウントの対象となっている子については、日本国内に住所を有しなくなった日から4年以内のものであること
該当する場合は、以下の書類が必要です。
(18歳到達後の最初の年度末までの児童の場合)
海外留学に関する申立書(児童用)(PDFファイル:191KB)
(18歳到達後の最初の年度末から22歳到達後の最初の年度末までの支給対象児童の兄姉等の場合)
海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)(PDFファイル:195.5KB)
(共通)
在学証明書等、留学している事実を証明する書類(外国語で記載されている場合は、国内に居住する第3者の翻訳が必要です
父母が海外にお住いの場合
日本国内に居住する児童の生計を維持している海外居住中の父母等が、日本国内で児童を養育する者を指定した場合、その指定された者が児童手当を受けることができます。
父母の一方が海外に居住する場合
父母のうち、一方が海外に居住する場合は、他方の国内で子どもを養育する方が受給者となります。
受給者が国外転出した場合は、国内で子どもを養育する配偶者の方から新たに手当の申請手続きが必要です。
父母が離婚協議中等により別居している場合
児童と同居している父母いずれかが優先的に受給できます。
以下の書類が必要です
- 離婚前提の別居の場合
受給資格に係る申立書(同居父母)(PDFファイル:144.9KB)
受給資格に係る申立書(同居父母)(Wordファイル:31.6KB)
離婚協議中であることを明らかにできる書類(離婚協議の申し入れにかかる内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書など)
- 離婚に伴う別居の場合
受給資格に係る申立書(離婚に伴う)(PDFファイル:137.3KB)
受給資格に係る申立書(離婚に伴う)(Wordファイル:31.5KB)
離婚の事実を証明する書類(離婚の受理証明書、離婚の記載のある戸籍謄本等)
受給者の子でない児童を養育している場合
以下の書類が必要です
配偶者からの暴力等により,住民票の住所地が泉南市と異なるとき
以下の書類が必要です
児童手当の受給に係る申立書(配偶者からの暴力)(PDFファイル:83.6KB)
下記のいずれかを証明することができる書類
- 裁判所から夫に接近禁止命令や退去命令などの保護命令が出されている
- 家庭支援センター等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されている
- 住民基本台帳の閲覧等の制限に係る申出をし、当該支援措置の対象となっている
(注)申請者及び児童が健康保険において配偶者の被扶養者となっていないこと
受給者が死亡した場合
児童手当の受給者が亡くなった場合、亡くなった日で児童手当の受給資格が消滅します。
亡くなった方に代わって児童を養育する保護者の方は、新規認定請求を行ってください。受給者の方が亡くなった日の翌日から15日以内に申請すれば、亡くなった日の翌月分から児童手当を受給することができます。
受給者が亡くなった時期によっては、未支払いの手当てがある場合があります。
その場合は、請求していただくことで児童の口座(支給対象児童が複数いる場合は1番年上の児童)にお支払いします。
寄付を希望される場合
手当の支払いを受ける前に申し出ることにより、児童手当等の全部又は一部を寄付することができます。
希望される場合はお早めにご相談ください。
現況届
現況届は毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。令和3年度までは全受給者に提出をお願いしていましたが、令和4年6月分以降は受給者の状況を公簿等で確認できる場合は、現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、以下の1~5の方は引き続き現況届の提出が必要です。
現況届の提出が必要な方には6月に市から現況届を送付しますので必ずご提出ください。
(1)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(2)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(3)配偶者からの暴力等により住民票の住所地が泉南市と異なる方
(4)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(5)その他、市で現況届の提出が必要と判断された者
提出の案内があった方で現況届の提出がない場合は、6月以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
受給証明書交付申請について
年に1回、支払予定日を記載した年次支払い通知書を送付します。奨学金の申請をする際に必要となることがありますので、大切に保管してください。
通知書を紛失された方は、再発行することもできます。必要書類を持参のうえご申請ください。
なお、通知書発行は、申請日から1週間程度かかることがありますので、余裕をもって申請してください。
申請・問合せ先
家庭支援課 電話番号 072-483-3472(直通)
この記事に関するお問い合わせ先
子ども給付係
〒590-0592大阪府泉南市樽井一丁目1番1号
電話番号:072-483-3472
ファックス番号:072-483-7667
e-mail:kateishien@city.sennan.lg.jp
お問い合わせはこちらから